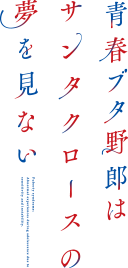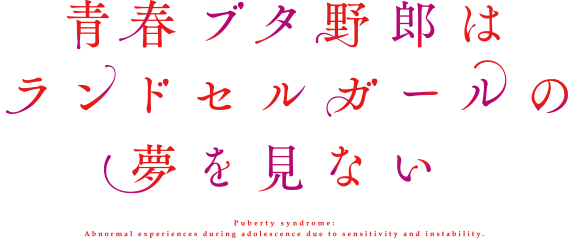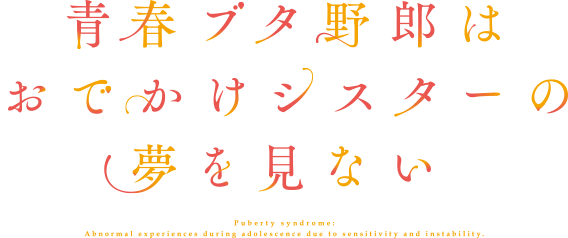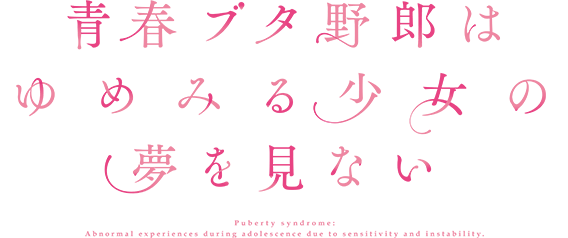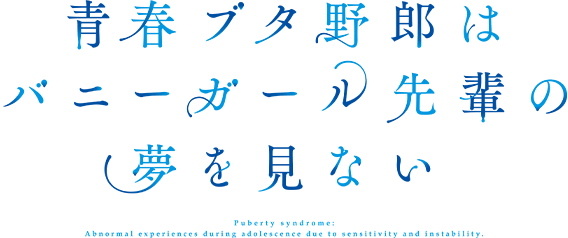Special スペシャル
「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」
原作者・鴨志田 一×監督・増井壮一
連載インタビュー
《サンタクロース編》
原作者・鴨志田 一×監督・増井壮一
連載インタビュー
《サンタクロース編》
岩見沢寧々について伺います。このキャラクターはいつ頃から考えられていたのでしょうか?
鴨志田一
(以下、鴨志田)
(以下、鴨志田)
大学生編を書くにあたって、一人のラスボス的な登場の仕方をしてくれる人物として、最初から決めていたキャラクターではあります。内面や細かい設定は、話の筋を組みながら考えていきました。
ミニスカサンタというのは絵面としてもインパクトがあります。
鴨志田
そうですね。ミニスカサンタの格好でうろついていれば存在感が出るだろうという安易な考えによるものです(笑)。バニーガールでうろついていた麻衣さんとも重なる要素として、この姿にしています。あと、咲太が高校生の頃からしていた「将来サンタクロースになりたい」といった発言にも紐づけられるかなと考えました。

寧々は大学生編を通じてメインヒロインではない話数にも度々登場していましたが、アニメで描写する上で注意されたことは何でしょうか?
増井壮一
(以下、増井)
(以下、増井)
彼女は咲太と美織以外の誰からも見えていないのですが、本人はそのことをまったく気にしていない人として描きたかったです。なので、「存在しているけど見えない人」である見せ方については注意しました。バニーガールの現象の再来みたいな感じなので、画面上では見えていますが、作中の人からは見えない描写をどのようにアニメとして表現するか、頭を悩ませました。
キャスト選定の決め手はどこにありましたか?
増井
まず、寧々が視聴者から「うざい人」と見られることは絶対に避けたかったです。彼女の言うことをきちんと聞いてほしいと思ったので、キャスティングの際はそこを重視して選ばせてもらいました。寧々が泣き叫ぶシーンがあるのですが、僕はオーディションで上田さんのお芝居を聞いた時に不愉快に思わなかったのが選んだ決め手でした。
鴨志田
まさに増井監督がおっしゃったことに尽きます。僕も同じくその嘆きのシーンでした。お芝居が真に迫っている感じで、上田さんに頼めてよかったです。
岩見沢寧々とはどんなキャラクターでしょうか? 人物像の解説やアニメにおける描写の工夫を教えて下さい。
鴨志田
寧々は大学生が悩みそうなことを入れた子なのかなと思っています。なので、彼女自身も普通の子ではあるんです。学生にとって就職というものは避けては通れない事柄としてありますが、彼女が「なれると思っていた仕事や存在」と「それになれないかもしれない」と迫る現実について、一度きちんと描いてみようと思って描いたキャラクターです。
増井
岩見沢さんは、彼女自身はすごく真剣に悩んでいるけど、「いやいや、まだまだ21、2歳でしょ?」、「これからじゃないの?」と、大人から見ると呆れちゃうような可愛らしさや必死さを出したかったです。作中でそれを代弁してくれるのは咲太です。咲太も後輩なんだけど、精神的には先輩のはずで、寧々に対するツッコミ役として立ってくれています。
最終的に彼女が「ずっと強がっていたけど、実は可愛い人なんだな」と視聴者に思ってもらいたいなと考えていました。彼女は口に出しませんが、やっぱりミニスカサンタの格好でうろついていた時は、かなり孤独だったんじゃないかと思います。でも、人柄的にはそういう面を見せない、高飛車な感じであるとともに、その脆さみたいなものが見えたらいいなと思っています。
最終的に彼女が「ずっと強がっていたけど、実は可愛い人なんだな」と視聴者に思ってもらいたいなと考えていました。彼女は口に出しませんが、やっぱりミニスカサンタの格好でうろついていた時は、かなり孤独だったんじゃないかと思います。でも、人柄的にはそういう面を見せない、高飛車な感じであるとともに、その脆さみたいなものが見えたらいいなと思っています。

福山拓海はどんなキャラクターでしょうか? 人物像の解説やアニメにおける描写の工夫を教えて下さい。
鴨志田
拓海は“良いヤツ”ですね。高校時代の咲太の男友達である国見佑真が消防士になってしまったので、日常でフラットに喋れる性格の人物という位置付けで生み出したのが拓海というキャラクターです。最初から設定として寧々と絡む役割は持たせてはいました。
増井
福山くんは北海道出身というのが自分の中でひとつポイントでした。僕にも北海道の友人がいて、絵面には別段出てこないかも知れませんが、あくまで気持ちの上として広々とした感じというか、おおらかで「何も問題ないでしょう」という雰囲気を出したいと思っていました。他の人と比べてもすごく自然体で、年相応であってほしいなと思っていました。

それぞれのキャラクターはさまざまに現代的な問題意識を抱えていますが、どのように考えて生み出されていったのでしょうか?
鴨志田
思春期症候群の原因となるような事象については、よく世間で言われているようなことや、ドキュメンタリー番組で取り上げられるような社会での一般的なことを題材にしているつもりです。そこから「みんなに悩みがあるとしたらこういうことだろうな」という題材をピックアップし、ひとつずつ掘り下げていく作り方です。その過程で人に話を聞いたりすることもありますが、99パーセントは創作です。あくまでキャラクターが魅力的に見えるようにしたいので、題材と行ったり来たりしながら作っていきます。
『青ブタ』のキャラクターは、どんどん地に足がついたキャラクター造形になっていったので、あまり突飛なことはせず、人間の思考としては「こういう出来事があったら普通にこう考えるだろうな」ということを頭の中で連想して考えを巡らせ、それと悩みの出来事をくっつけて思春期症候群が起こるという作り方をしています。
本質的に人間が悩むことなんて、時代が変わってもそんなに変わらないと思っているんですよね。悩みの強度やその時代で用いるアイテムの違いなどはあるにせよ、全くその気持ちが理解できないということはたぶんないので、そこを自分の中で育てていけば、その感情はキャラクターの悩みになると思います。
『青ブタ』のキャラクターは、どんどん地に足がついたキャラクター造形になっていったので、あまり突飛なことはせず、人間の思考としては「こういう出来事があったら普通にこう考えるだろうな」ということを頭の中で連想して考えを巡らせ、それと悩みの出来事をくっつけて思春期症候群が起こるという作り方をしています。
本質的に人間が悩むことなんて、時代が変わってもそんなに変わらないと思っているんですよね。悩みの強度やその時代で用いるアイテムの違いなどはあるにせよ、全くその気持ちが理解できないということはたぶんないので、そこを自分の中で育てていけば、その感情はキャラクターの悩みになると思います。
アニメの演出として意識していることは何でしょうか?
増井
大まかな部分ではほとんど脊髄反射のように行なっているので、意識しているかと聞かれると、そこまでのことはなく、ほとんど直感的に行なっていることばかりです。たぶん、僕自身の心が高校から大学生のままなのでしょう(笑)。自分自身はそんなに大人のつもりではない」と思っているんで、年代的なズレを感じていないつもりでいます。
高校の時に持っていた違和感は、今でも違和感を持ち続けているので、本質的に変わっていないのかなと。小説で鴨志田さんがそのあたり具体的に描写されているから、それに素直に従って出していけば良いんです。その意味で、自分は文字を絵にする変換機のような立場だと思っているので、迷いなくできているかなと思っています。
高校の時に持っていた違和感は、今でも違和感を持ち続けているので、本質的に変わっていないのかなと。小説で鴨志田さんがそのあたり具体的に描写されているから、それに素直に従って出していけば良いんです。その意味で、自分は文字を絵にする変換機のような立場だと思っているので、迷いなくできているかなと思っています。